
双六大会で

双六大会を様々な場所で開催しています。
そのたびに、双六の力、遊びの力ってすごいなぁと、主催者である私たちが驚いています。
兵庫県主催のふれあいフェスティバルに出展参加した時のことです。
6人一組になっていただき、双六大会はスタートします。参加者は初対面の方々ばかりです。老いも若きもひとつの双六盤を囲み、上りを目指します。
初対面同士ですから、固い空気でゲームはスタート。が、中盤になるころにはゲームは白熱し出し、お互いの雰囲気に変化が見られます。
手の届かないコマを移動したり、サイコロを手渡したりして、やがて笑い声がおこり、祝福や悔しい!の声が飛び交います。まるで家族が遊んでいるような打ち解けた空気が流れ始めるのです。
もちろん、振出しに戻れのマスに出くわして、泣いてしまう子も出てきます。それだけ本気になってしまっているのでしょう。
子ども達だけだけかと思えば、さにあらず。一番積極的なのは高齢の男性なんてこともあるのです。
私がほほえましく、そして驚きを持って見つめてしまう光景は、お子さん方と見知らぬ高齢の方々との距離感の変化です。
人見知りでお母さんの傍から離れない小さなお子さん。これはどんなイベントでもよく見る光景です。お嬢ちゃんであったり、坊ちゃんであったり、それぞれですが、ふと気が付けば、気が付けば初対面の老婦人の膝に座って双六をしていたり、高齢紳士の手を握ってともに喜んでいたり…。まるで孫とおじいちゃんおばあちゃんのように、身を乗り出して楽しそうに遊ぶ姿は、実に印象的です。
その姿に私どもも驚いたものですが、一番びっくりなさったのは、当のおかあさんでした。
「人様にこんなに懐いているところを見たことがない…」
そうおっしゃいます。
「とてもとても、そうは見えませんわね!」私もうれしくなって、そのように答えたのを覚えています。
様々な事件も起こる昨今です。「人懐っこさ」をあえて封じなければならない時代でもあるのです。しかし、子供の「人懐っこさ」は興味の入り口。またご高齢の方々の寛容さや懐の深さは、次世代を育てる献身。この関りをあえて諫めねばならない現実社会を、悲しく思う瞬間でもありました。
「場があればいいのだ」
双六は場創りに一役買えましょう。
そういえば、大学の授業で双六大会を開催した時のこと。
友達以外で遊ばせようとしたところ、それぞれが面倒くさそうな表情をするのです。
「授業ですよ!あきらめてさっさとお始めなさいな。」
不満があってもやるしかありませんものね。単位は欲しいですから。でも私どものはわかっていました。どうせ始まれば、精一杯楽しむようになることを。
思惑通り、途中から笑い声が聞こえてきました。「ほらね!だから言ったでしょう!」と、口に出さないまでも、心の中で私は、したり顔でした。
ちゃんとした授業ですから、最後に感想等含んだちょっとしたレポートを提出させます。アンケート程度のものではあるのですが、そこに見られるのは
同じ教室でも話したことがない人と親しくなれてよかった。
という感想。双六は最強のコミュニケーションツールだと再確認しました。
自然界で動物の赤ちゃんはひたすら遊びます。遊ぶことが学びに直結しています。「夢中になって遊ぶ」は「夢中になって学ぶ」ことでもあるのです。しかしそれが、今のいわゆるゲームだったらどうなのでしょう。様々なゲームの問題が取りざたされていますよね。
果たして、あのコンピューターゲームの中に学びはないのでしょうか。
友人は仕事上で策を練る時に、ゲームの布陣が浮かんでくると言います。別の友人は、コツコツと働き積み重ねることの大切さとその資質が自分にあることを、牧場物語というゲームの中での自分に学んだと言います。別の友人は、「資産を増やすってどういうことなのか」をいただきストリートのゲーム上で、ぼんやりと覚えたと言います。
そうそう、こんなことも聞いたことがあります。
「人を呪わば穴二つ」
これを、桃太郎電鉄シリーズで学んだと。そして、どん底になってから這い上がるまでの自分(ゲーム上の自分でしょうが)を楽しんだと。決してリセットせずに進めば、いつか空気が変わる時があるのだそうです。
その手のゲームを大してしない私には到底わからないことなのですが、みな「薄っぺらい人間」ではありません。向き合い方と「学ぶ土壌」が、ゲームに夢中になる以前に、持ち合わせていたのだろうとは思います。それを育てたのはご家庭での教育もありましょうが、想像力の芽があるのか否かは大きいと思います。共通していたことは、「読書家」であったことでした。そして、会話がある家に育っていました。
さておき、「三つ子の魂」を育てることのお手伝いを、私どもの使命の一つにすることの大切さを考えます。
私たちは遊びの中に、もう少しだけ学びのエッセンスを加えて双六を作成しています。
遊びの力を信じながら、楽しい学びの入口へと誘うことができればと願っているのです。
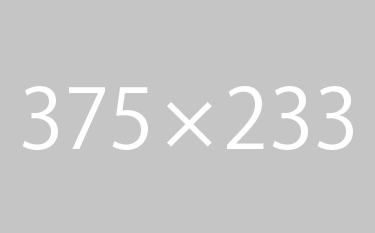



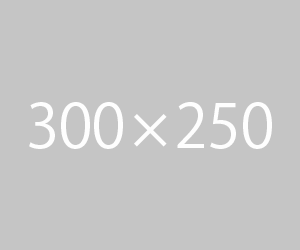
この記事へのコメントはありません。